R1 The Attic Tapes (2015) Riverboat Records
|
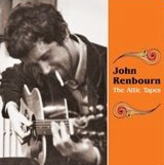 |
John Renbourn: Guitar (Except 14), Harmonica(14), Vocal
Mac Macleod: Guitar (14.16), Vocal (14,16)
Beverley Martyn: Vocal (4,10)
Davey Graham: Guitar (20), Vocal (20)
1. Anji [Davy Graham] R13 R20 V2 K2
2. Blues Run The Game [Jackson C. Frank] R3 R17 R29 Q5 Q17
3. Rosslyn
4. Picking Up The Sunshine (Live) [Donovan Leitch] Q4
5. I Know My Babe (Live At Les Cousins)
6. The Wildest Pig In The Country R3 R3
7. Candyman R3 R13 R20 V2
8. Buffalo R4 K1 K4
9. National Seven (Live) [Alan Tunbridge] R3 R29
10. Come Back Baby [Trad. arr. John Renbourn, Beverley Martyn]
11. Train Tune (Live) R3
12. Judy (Live) R3 R20 V2 K1 K2
13. Beth's Blues (Live) R3
14. Cocaine [Trad. arr. Mac MacLeod] R29
15. Courting Blues [Bet Jansch]
16. It Hurts Me Too [Trad. arr. Mac MacLeod]
17. Portland Town (Live) [Derroll Adams] T16
18. Plainsong (Live) R3
19. Can't Keep From Crying (Live) R3 R4 R27 T14 V9
20. Nobody Knows You When You're Down And Out (Live) [James Cox]
注: 3. 5.は既発映像(V7) と同一の音源 なので、カバー番号の表示は行いません。
|
ジョンのファンになってから、長い間クラシカルな曲と演奏が好きだったが、2010年代後半になってからは、何故か初期のスタイルに愛着を覚えるようになった。主にジャズのリズム・ギターで使われた、スカースというブランドのメイプル・ボディの古いギターは、サステインが少ないためフィンガー・ピッキング向きではないが、逆に歯切れが良い乾いた音がでるメリットがあったと思う。ジョンはそのギターの弱点をカバーするためにタッチを強くし、そのうえで特性を生かして、強靭なリズム感と驚異のフィンガリングで、あの独特な「乗り」を生み出したと言える。ここでのスリーフィンガーによる音使いは、アメリカのブルース・ギターをベースとした独特なもので、「There
You Go」1965 R2、「John Renbourn」 1966 R3、「Bert And John」1966 T1等で聴くことができる。そのスタイルは、多くのギタリストに大きな影響を与えながら、同じ音を出せる人は皆無という絶対的な個性となった。彼自身も、マホガニー・ボディのギブソンJ50に持ち替えた「Another
Monday」R4 1967を過渡期として、さらにローズウッド・ボディのギルドを使用し始める過程で、優しいタッチで洗練されたクラシカルな演奏をするようになったが、その代償として、当初の持ち味だった「乗り」が失われたと言える。
録音されてから50年以上経ってから発掘された音源を収めた本アルバムは、初期の演奏スタイルをたっぷり満喫することができ、私のようなファンにとっては最高の贈りものとなった。この手の作品にありがちな音質面の問題もなく、普通のギター音楽として十分楽しむことができることも素晴らしい。本アルバムは2015年10月に発売されたが、制作に携わりライナーノーツも執筆したジョンが
2015年3月15日心臓発作のためこの世を去ったこともあり、生前最後となったアルバムがこのような原点復帰の企画になったことは感慨深い。
1961年から1964年までジョンと一緒に演奏していたマック・マックロード(1941-2020)が、当時の録音テープを持ち込んだことがきっかけで、他の音源と合わせて本アルバムが制作されたという
(タイトルの「屋根裏のテープ」は、「長い間眠っていた」という意味)。 1.「Anji」は中でも貴重で、ジョンのライナーによると、彼は、デイヴィーが1962年に自身のEPレコード「3/4
A.D.」で発表する前に、友人から教えてもらったものと推測している。そのためか、テーマ部はデイヴィーの演奏と大差ないが、間奏部分は全く異なる内容で、ジョンのスタイルそのものになっているのが凄い。若さ溢れる切れ味鋭いプレイは、この曲のベストバージョンのひとつと断言できる。各曲の録音時期・場所の記載がないので、はっきりしたことはわからないが、時期こそは異なるかもしれないが、同じ状況で録音されたものと推定されるのが、2.「Blues
Run The Game」、6.「The Wildest Pig In The Country」、8.「Buffalo」、15.「Courting
Blues」。スカース・ギターの音から1962年〜1966年の間の録音であることは間違いない。2.は「So Clear (Sampler Vol.2)」
1973 Q10、6.は「John Renbourn」 1966 R3、8.は「Another Monday」 R4 1967に収録された公式録音の別テイク的な感じで、ちょっとした部分の演奏内容の違いを楽しむことができる。15.「Courting
Blues」は、バート・ヤンシュのファーストアルバムに収められた曲のカバーという珍品。録音当時、彼に会ったことはなく、レコードもなかったので、友人から習ったものという。歌伴の部分は同じ音使いでありながら「乗り」が違うし、間奏部分はレンボーン節になるところはさすがです。9.「National
Seven」、11.「Train Tune」、12.「Judy」、13.「Beth's Blues」、17.「Portland Town」、18.「Plainsong」、19.「Can't
Keep From Crying」は、曲後に拍手が入るライブ音源。 17.「Portland Town」は、ランブリン・ジャック・エリオットと一緒にアメリカからやってきて、その後ヨーロッパ(イギリス、ベルギー等)に留まり同地のフォーク・シーンに大きな影響を与えたデロール・アダムス
(1925-2000)の代表曲で、戦争で息子を失った父親の嘆きを歌っている。1991年彼の75歳の誕生日を記念してベルギーで開催されたコンサートの実況録音が発売され、そこではペンタングルが数曲演奏しており(T15,
T16参照)、フィナーレでは全員で同曲を歌っている。
14.「Cocaine」、16.「It Hurts Me Too」は、前述のマック・マックロードとのセッション。彼はその後ドノヴァンを親交を深めた後、ギタリスト、ベーシストとしてイギリスのロックシーンで活躍。
2000年代以降はドノヴァン、ジョンとのリユニオンを果たしたそうだ。14.でジョンはギターを弾かず、シンプルであるが味のあるブルース・ハーモニカを吹いている。16.は二人のフィンガーピッキングによる演奏で、マックがリードボーカルを担当し、ジョンが時々加わる。
4.「Picking Up The Sunshine」、10.「Come Back Baby」は、本アルバムもうひとつのハイライトで、ベヴァリー・マーティン(1947-
)との共演ライブ録音だ。彼女は1965年16才の若さで、在籍グループのボーカリストとしてシングル・デビューし、後にデラム(Deram)というレーベルと契約して、シングル・レコードを発表。そこにはレッド・ツエッペリン結成前のジミー・ペイジ、ジョン・ポール・ジョーンズ、セッションマンとして名高いニッキー・ホプキンス(ピアノ)、アラン・ホワイト(ドラムス、おそらく後にYesに加入した人、同姓同名かもしれない)がバックを担当した。彼女の3枚目のシングルとしてドノヴァンの「Bert's
Blues」のカヴァー「Picking Up The Sunshine」が録音されたが、彼女がレーベル・オーナーと音楽上の意見の相違で衝突したため、B面に収められる予定だった「Gin
House Blues」とともに未発表となった。この2曲には、前述のスタジオ・ミュージシャンに加えて、ジョンがアコースティック・ギターで参加しているというが、聞いた限りでは他の楽器の音にかき消されて、アコギの音ははっきり聴きとることができない。なお本アルバム発売後の2017年にFly
Recordというインディ・レーベルがレコードストア・デイズのイベントとして前述の2曲を含むレコードを限定盤で発売し、50年ぶりに聞くことが出来た(Q4参照)。前置きが大変長くなったが、本アルバムに収められた4.「Picking
Up The Sunshine」は、ジョンのギター伴奏によるライブ録音。彼女の歌声には、聴くもの心に届く力強さがあり、ジョンのギター演奏と合わせ素晴らしい出来だと思う。彼女は当時バート・ヤンシュにギターを習っていたそうで(そのためバートのアルバム「It
Don't Bother Me」1965の表紙写真に彼女が写っている)、その関係でバートのレパートリーだった10.を歌っているものと思われる。ジョンのギターもバートと全く異なる内容で、二人の個性の違いが際立っている。ここで余談をひとつ。当時のベヴァリーは「Beverley
Kutner」という旧姓で、バートと付き合った後、ポール・サイモンと仲良くなり、彼の招きでアメリカに渡る。サイモン・アンド・ガーファンクルで有名になった後、彼らが1967年に制作したシングル「Fakin'
It」(後にアルバム「Bookends」 1968に収録)の歌唱の合間に出てくる「Good Morning Mr. Leitch. Have
you had a busy day?」という若い女性の語りは、彼女が担当していたのだ!! これは本文執筆にあたり、関連資料を読んでいるうちに判った話。私は当時このレコードを愛聴していて、誰かはわからなかったが、この知的な雰囲気が溢れた声に魅了されていただけに、50年後になってこのような形で結び付いた事に感動してしまいました。ベヴァリーは、その後1969年にフォークシンガーのジョン・マーティン(1948-2009)
と恋に落ち、結婚してBeverley Martynとなる。二人名義のアルバムを2枚発表後、ベヴァリーは引退して家事・育児に専念するが、1970代に夫の薬物・アルコール中毒、家庭内暴力が原因で離婚。その後彼女は1990年代に音楽活動を再開した。
3.「Rosslyn」は1974年9月1日に放送されたBBC放送の「The Five Faces Of The Guitar」というTV番組での演奏。ジョン(フォーク)の他に、ジュリアン・ブルーム(クラシック)、バーニー・ケッセル(ジャズ)、ジェフ・ベック(ロック)、パコ・ペナ(フラメンコ)という、各ジャンルの達人が登場して、語り演奏するという教則的な内容だったという。ブルースと古典音楽の融合を目指した作風で、「Black
Balloon」 1979 R14 の「The Perican」のテーマを連想させるリュートのようなテーマと、途中のブルース的な展開との対比が大変鮮やかな名曲。同番組で演奏した他の1曲.「Blues
In A」も収めて欲しかったなあ(詳細はV7を参照ください)。なおジョン・レンボーンのホームページでタブ譜が公開されている。15.「I Know
My Babe」は、デンマークのテレビ局もよる撮影で、1965年ペンタングルが根城としたライブハウス「Les Cousins」での演奏という貴重なもの。若さ溢れる演奏が最高で、テレビ放送用のため音質も良い。映像を観たい人はV7を参照ください。
ということで、初期のレンボーンを好む人にとって宝物のようなアルバムとなった。ありがたや、ありがたや..........
[2020年1月作成]
|
| R2 There You Go (1965)E.M.I. Columbia Records SX6001 |

 |
〔Dorris Henderson And John Renbourn〕
Dorris Henderson: Vocal
John Renbourn: Guitar, Vocal (6)
Guy Robinson: Producer
Brian Shuel: Cover Photo, Design
Dave Moran: Liner Notes
[Side A]
1. Sally Free And Easy [C. Tawney] T7 T12 T16 T17 T18
2. Single Girl [Trad.]
3. Ribbon Bow [Trad.]
4. Cotton Eyed Joe [Trad.]
5. Mr.Tambourine Man [Bob Dylan]
6. Mist On The Mountain [Renbourn, Warren]
7. The Lag's Song [MacColl]
8. American Jail Song [Trad.]
9. The Water Is Wide [Trad.]
[Side B]
10. Something Lonesome [Renbourn] Q1
11. Song [Donne, Renbourn] R3 T3
12. Winter Is Gone[Trad.] R3
13. Strange Lullaby [Piepe, Renbourn]
14. You're Gonna Need Somebody On Your Bond [Trad.]
15. One Morning In May [Trad.] V9
16. A Banjo Tune [Trad.]
17. Going To Memphis [Trad.]
15.はレンボーン非参加、 インストルメンタルはなし
レンボーン、ヘンダーソン自身による曲についての簡単な解説付き
1966年 2月発売
[Bonus Track for Reissue CD Big Beat CDWIKD 186 1999]
18. Hangman [Trad.]
19. Leaves That Are Green [Paul Simon]
(1965年のシングル・レコードより)
〔楽譜掲載〕 12 G3
注) 上の写真はオリジナル・レコード盤のジャケット (E.M.I Columbia)
下の写真はCD再発盤のジャケット(Big Beat))
|
ジョン・レンボーンのレコード・デビュー作。私がこのレコードの存在を具体的に知ったのは、イギリスの専門誌「フォーク・ルーツ」1993年4月号のマギー・ホランド氏による記事から。それ以前もインタビュー等でほんの僅か言及される程度で、日本ではほとんど紹介されていなかった作品。1965年アメリカからやって来た黒人歌手のドリス・ヘンダーソン
(1933-2005) と知り合い、意気投合してデュオを結成、録音したのが本作である。彼女のソロ・アルバムということで、ジョンは単なる伴奏者に過ぎないのではと思い込んでいたが、クレジットは「Dorris
Henderson And John Renbourn」となっており、ジョンのカラーも十分に出ていて実質的に共同制作と言える。ジャケットの表紙も二人が仲良く向き合っているカラー写真によるもので、若々しいジョンの手に握られているのは、彼のファースト・アルバムの表紙にも写っている、あのScarth
Guitarだ。この素晴らしいジャケット写真はブライアン・シューエルによる撮影で、彼はバートやジョンのトランスアトランティック初期アルバムの表紙を撮影した人物。ちなみに上述のフォーク・ルーツ誌にこの写真の別テイクが掲載されている。ドリスは説教師の娘で、ソウルフルで太く、よく響く声を持つシンガー。黒人音楽としてのブルースにこだわらず、アパラチアン地方のバラッド、ワークソング等トラディショナル・ソングに対する深い造詣と幅広いレパートリーを誇る。後年彼女はジョンのソロアルバム「Faro
Annie」 1971 R7 にゲスト出演している。伴奏のジョンのギターは、少々控え目であるがファースト・ソロアルバムとほぼ同じサウンドであのビンビンのブルース、スリーフィンガー・ピッキングを存分に楽しむことができる。
1.「Sally Free And Easy」はペンタングルの「Solomon's Seal」 1972 T7 でお馴染み。ここではストレートな歌唱と素晴らしいギターの間奏を聴かせてくれる。2.「Single
Girl」、8.「American Jail Song」ではジョンお得意のブルース・ギターが良い出来。5.「Mr. Tambourine Man」は当時ヒットしていたボブ・ディランの名作のカバー。6.「Mist
On The Mountain」はジョン、ドリスのデュエットによる小品。9.「The Water Is Wide」は多くの歌手が歌うトラッドの傑作。B面の最初の曲10.「Something
Lonesome」はジョンのオリジナルで、ギター演奏はレンボーン・スタイルのルーツと言えるもの。ここではドリスの歌が入っているが、このギター・パートが後にバート・ヤンシュとのデュエット「Lucky
Thirteen」 に応用される(バートのソロアルバム「It Don't Bother Me」1965 Q1に収録)。11.「Song」はジョンのファースト・ソロアルバムにも収録された。「このエリザベス朝時代の詩人の女性や愛に対する考えは、ボブ・ディラン、ジャクソン・C・フランクやバート・ヤンシュが求めているものと似ている」という、ジョンの解説が興味深い。14.「You're
Gonna Need Somebody On Your Bond」はボトルネックを使ったブルースギターが渋い。15.「One Morning
In May」は彼女の独唱。2005年の映像 V9では、ジャッキ・マクシーが一人で歌っている。16.「A Banjo Tune」はバンジョーを思わせる素早いピッキングとドリスの伸びのある声が秀逸。17.「Going
To Memphis」はドリスのナレーションから始まるジェイル・ソングで、乗りの良い演奏で二人とも気持ち良さそう。
常に直球勝負の剛速球投手のようなパワーに溢れ、聞き終わると疲れを覚えるほどで、当時の若々しい息吹と二人の音楽的な一体感が素直に表現されており、十分に聴き応えのある作品である。本作はコレクターズ・アイテムとして長い間入手困難だったが、1999年フォーク・ルーツ誌の主導により、念願のCD再発が実現した。ただしジャケット写真はオリジナル盤と異なる。有難いことに当時発売されたシングル2曲が追加された。特に19.「Leaves That Are Green」はサイモンとガーファンクルの初期の名曲。地下室で録音したような音質で、ウッドベースの音が聞こえる。ちなみに再発盤の解説は、1998年に行われた彼女(今も歌手として活躍している)とのインタビューを含み、当時の雰囲気を生き生きと伝える素晴らしい内容。
彼女との共演は、1967年の作品「Watch The Stars」 Q6 に続き、その後はジョンのソロアルバム「Faro Annie」 R7
1971などがある。ジョンがギタリストとして確固たる名声を獲得したのに対し、ドリスのその後は不遇で、参加レコードもあまりない。上述の記事および本作のCD化により再評価の気運が高まった彼女は、2003年にソロアルバム「Here
I Go Again」Q30を製作、ジョンが2曲に参加している。
|
R3 John Renbourn (1966) Transatlantic Records TRA135
|
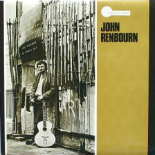 |
John Renbourn : Guitar, Vocal
Bert Jansch : Guitar (8,15)
Nathan Joseph : Producer
Brian Shuel : Cover Photo, Design
[Side A]
1. Judy * R1 R20 V2 K1 K2
2. Beth's Blues R1
3. Song R2 T3
4. Down On The Barge *
5. John Henry [Trad.]
6. Plainsong * R1
7. Louisiana Blues [Muddy Waters]
8. Blue Bones * [Renbourn, Jasch]
[Side B]
9. Train Tune * R1
10. Candy Man [Trad.] R1 R13 R20 V2
11. The Wildest Pig In Captivity * R1 R3
12. National Seven R1 R29
13. Motherless Children [Trad.]
14. Winter Is Gone [Trad] R2
15. Noah And Rabbit * [Renbourn, Jasch]
[Bonus Tracks for Reissue CD Sanctuary CMRCD359 2001]
16. The Wildest Pig In Captivity * R1 R3
17. Can't Keep From Crying [Trad.] R1 R4 R27 T14 V9
18. Blues Run The Game [Jackson C. Frank] R1 R17 R29 Q10 Q17
〔楽譜掲載〕 1: K1 K2 G1 G2 G10、F1、 3,10 : G3
レンボーン自身による簡単な曲の解説付き
|
|
ジョン・レンボーンのソロ・デビュー作は、ブルースなどアメリカン・ミュージックにどっぷり浸かった若々しい演奏を聴くことができる。バートの「It
Don't Bother Me」 1965 Q1の録音の後、ステージ活動等の実績が認められ、レコード製作のオファーを受けて録音。プロデュースはトランスアトランティックのオーナー、ネイサン・ジョセフ。録音時期は前作
R2よりも前らしい。
本作における彼のギターは若々しく荒っぽさにあふれている。ほとんどの曲がアメリカ風のブルースであり、中世音楽やブリティッシュ・トラッドへの傾倒はまだ見られず、当時のイギリスにおけるアメリカン・フォーク、ブルースの流行が偲ばれる。バートとの共演作8. 15.を除き、彼一人の演奏で少々単調な気もするが、彼のブルースとスリーフィンガーのギターと、よく聞き込むとそれなりに味がある歌声を十分に堪能できる。ジャケットの撮影とデザインは、バートの初期の作品でもお馴染みのブライアン・シューエルで、この人のセンスは本当に凄い。ギターを持った若いレンボーンの写真とシンプルなタイトル・ロゴ、全体を覆うセピアの色調が、この作品の内容を何よりも物語っている。1965年のバートのデビュー作(そのジャケットの色調により別名「Blue Album」ともいうそうだ)とともにジャケット・デザインの傑作だと思う。ちなみに写真のギターは Scarth というメーカーの古いアーチド・トップ・ギター(ラウンドホール、テールピース付)で、ダンスバンドのリズムギター等でよく使用されていたものという。ジャンゴ・ラインハルト初期の1934年の写真(愛用のセルマー製のギターを手にする以前)にそっくりなモデルのギターを持って写っているものがある。
1.「Judy」は恋人(後の奥さんとなるジュディ・クロス)の名前を冠した最初のインスト作品のひとつで、「Angie」風のスタイルはデイビー・グラハムの影響が濃厚。3つのパートから構成されたモダンなブルース調の小品で、彼の初期作品中リクエストの多いスタンダードとなった。ステージでは「Angie」とのメドレーで演奏される。前述の表紙写真のギターはサステインがない乾き切ったチープな音。おそらく「Bert
And John」 1966 T1 の録音の際も同じギターを使用していると推測される。6.「Plainsong」はシンプルなメロディーの反復が効果的で、途中から彼のハミングが加わり乗りの良い演奏。4.
9. 11.は彼独自の手数の多いスタイルによるモダンな感覚のブルース・フォーク調インスト曲。8. 15.はバート・ヤンシュとの共演でラフなジャム・セッション。アドリブ主体の曲でバートもソロをとっている。演奏中の咳の音も聞こえ、両者のギターのチープな響きが当時の空気を色濃く反映している。
歌ものは8曲。ブラインド・ボーイ・フラーの2.「Beth's Blues」は典型的なラグタイム・ブルース。5. 7. 13.はボトルネックによる演奏。スライドバーを小指にはめ、フィンガーピッキングとの兼用の演奏。10.「Candy
Man」はゲイリー・デイビスで有名なラグタイム・ブルース。この曲はドノバンやステファン・グロスマンのレパートリーでもある(ディランの初期の演奏も海賊盤で聴ける)。ギター・スタイルは音数の多い弾きまくるブルースが主体で、モノトニックとオルタネイトが交錯するリズミックで動きの激しい低音のピッキングとリズムの乗りに個性を感じる。ブルースといってもアメリカ人が演奏する様な泥臭さがなく、理知的で跳ねるような乾いた音になっているのが面白い。
ジョンのボーカルはお世辞にも上手いとは言えないが、独特の味わいがあり、そのフィーリングには当時のボヘミアン的な生活感が滲み出でいる。私にとってジョン・レンボーンは最初の頃はインストメンタルが目当てだったが、聞き続けて35年以上過ぎた今では、ボーカルものが非常にいとおしく感じる。なお3.
14.は前作 R2 でドリス・ヘンダーソンが歌っていたもの。
ジョンの音楽上の原点が素直に表現されたシンプルでストレートな一枚。
2001年に発売されたサンクチュアリー・レコードからの再発盤には、未発表曲が3曲収録された。いずれも本アルバムのアウトテイク、あるいはデモ録音と思われる。16.「The Wildest Pig In Captivity」は11.の別録音で、本作のブルース曲のなかでも出色の出来だけに貴重。16.のほうはキーが低くてゆっくり弾いている。テープスピードを操作しているとも思えないので、おそらくオリジナルの11.はカポをはめてキーを高くして弾いたのだろう。曲の切れ味では11.、リラックスした雰囲気という意味では16.だろう。17.「Can't Keep From Crying」はR4ではジャッキー・マクシーのボーカルだったが、ここでは彼自身が歌っている。18.「Blues Run The Game」は1973年のベスト盤「So Clear」 Q10 に未発表曲として入っていた曲であるが、これは別録音でギター伴奏も特にエンディングが異なっている。サンクチュアリー・レコードの他の再発盤と同様、詳しい解説の他に当時の写真やマスタテープの箱写真などの貴重な資料が添付されている。
|
R4 Another Monday (1966) Transatlantic Records TRA149
|
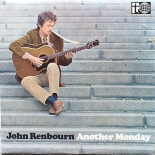 |
John Renbourn: Guitar, Vocal
Jacqui McShee: Vocal (5,10,12)
Jennifer de Montforte-Jones: Oboe (6)
Bill Leader: Producer
John Adams: Cover Photo
Brian Shuel: Cover Design
[Side A]
1. Another Monday *
2. Ladye Nothinge's Toye Puffe * R21 Q13 K1
3. I Know My Babe [Trad.] R13 V7
4. Waltz * T2 T3
5. Lost Lover Blues [Trad.]
6. One For William *
[Side B]
7. Buffalo * R1 K1K4
8. Sugar Babe [Trad.]
9. Debbie Anne *
10. Can't Keep From Crying [Trad.] R1 R3 R27 T14 V9
11. Day At The Seaside *
12. Nobody Fault But Mine [Trad.]
〔楽譜掲載〕 1,9,11: G1 G2、 2: K1 G1 G2 G10、F3、 3: G11、 6: G11、 7: K4 G1 G2 G11
F1
レンボーン自身による簡単な曲の解説付き
|
デビュー作と同じ年に発売された第2作目は、ペンタングル結成前最後のソロアルバム。前作におけるアメリカン・ブルースへの執着は残りながらも洗練度を増し、一方でその後のスタイルとなる中世音楽への嗜好の萌芽が見られる。表紙に写っているギターはギブソン
J-50。これはナチュラル・フィニッシュのトップ、マホガニーのサイド、バックからなる中級モデル。サンバースト・フィニッシュの J-45とともに当時の黒人ブルースマンに大変人気が高かったもので、ブルース好きな当時のジョンにとっては妥当な選択。初期のジェームス・テイラー等愛用者も多く、枯れた音が特徴。本作のプロデューサーはビル・リーダーで、この作品もバートの初期の作品と同様ホーム・レコーディングという。
ゲストとして当時デュオを組んでいたジャッキー・マクシーが3曲サイドボーカルで参加、彼女によると「初めての録音で夢中だった」そうだ。彼自身のライナーノーツで、「彼女の家があるサットンのレッド・ライオン・クラブで出会った若いシンガー」と紹介された。いずれも完全なアメリカン・ブルースで、彼女のような透き通った声の持ち主が低い声でブルースを歌うことで、独特の雰囲気が出ており大変面白い。5.「Lost
Lover Blues」はトラッドとあるがブラインド・ボーイ・フラーの作品。本作におけるトラッドはすべてアメリカンで、ブリティッシュものはない。12.「Nobody
Fault But Mine」 ではジョンのボトルネック・ギターのシンプルな伴奏が聴かれる。3.「I Know My Babe」は深みのある印象的なラブソングで、レオ・コッケ、ジェームス・テイラー、ザ・バーズ、グレイトフル・デッド等の多くのアーティストがカバーしているトラディショナルの名曲。(「I
Know You Rider」、「Circle Round The Sun」というタイトルでも知られる)その独特の音数の多いスリーフィンガーのギター伴奏とボーカルが良い出来。1996年に発掘された本曲の映像
V7は必見! 8.「Sugar Babe」のギターはバンジョーのフレイリング奏法のようなサウンド。
1.「Another Monday」は彼のブルース・スタイルの集大成で、必殺のブルース・リックをしつこい位連発。4.「Waltz」は3拍子のアップテンポの曲で、サウンド的にバート・ヤンシュの初期のインストに近い。なおペンタングルのデビューアルバム
T2 1968 にアンサンブル・バージョンが収録された。7.「Buffalo」はデイビー・グレアムのスタイルに近い作品で、ジャズの和声による当時最先端のジャズ・ブルース曲の典型。ジョンのブルースのなかでもコンパクトにまとまった佳曲。9.「Debbie
Anne」はさっぱりした味の小品。前半はスリーフィンガーで、途中から得意のブルース・ピッキングとなる。11.「Day At The Seaside」はライナーによると、「『
Living In The Country』という名前でバート・ヤンシュが演奏するインストルメンタル」とあるが、バートの演奏はレコード化されていない。スリーフィンガーによるマイナー調の小品であるが、どこかイギリスの匂いのする音である。
ギタリスト、ティム・ウォーカーとの共同作業の結果という 2.「Ladye Nothinge's Toye Puffe」は、中世音楽への傾倒を示した初めての作品で、彼のベスト曲のひとつとなった。中世音楽の和声、対位法にブルース・ジャズの和声がほのかにブレンドされ、素晴らしくモダンな曲に仕上がっている。ドロップド・D・チューニングによる演奏で、彼の作品のなかでもシンプルな美しさに溢れた飽きのこない曲。後にデュエット・パートが書き加えられ、ペンタングルの再結成コンサート・ツアーで演奏、またジョン・ジェイムスとのデュエット
Q13 や彼自身の多重録音 R21で2度再録音された。バートも自己のソロ作品「L.A. Turnaround」1974 でカバーし、ピーター・ラッツェンベックというオーストリアのギタリストによるカバー(「Over
The Year」1990に収録)もある。6.「One For William」はオーボエとの共演で、少しぎこちない出来ではあるが、そのクラシカルなサウンドは次作を予言している。ブルース一辺倒から中世音楽への傾斜の過渡期にある作品ながら、個人的には思い入れ深い愛聴盤。
|
| R5 Sir John Alot Of Merrie Englandes Musyk Thyng & Ye Grene Knyghte (1968) Transatlantic Records TRA167 |
 |
John Renbourn : Guitar
Terry Cox : Finger Cymbals, African Drums, Glockenspiel
Ray Warleigh : Flute
John Wood : Engineer
Nathan Joseph : Producer
Osiris(Visions) Ltd. : Sleeve Design
[Side A]
1. The Earle Of Salisbury [W. Byrd] R5 R13 T3 T10 K5
2. The Tree They Do Grow High [Trad.] R18 R19 R27 T3 T3 T10 T16
3. Lady Goes To Church
4. Morgana
[Side B]
5. Transfusion [Charles Lloyd] R5 R13 K1 K4
6. Forty-Eight [Renbourn, Cox] R5 T10
7. My Dear Boy K1 K4
8. White Fishes [Renbourn, Warleigh]
9. Sweet Potato [Booker T.Jones] R12 R20 R24 V3 V5 V7 K1K2
10. Seven Up [Renbourn/Cox]
1968年5月発売、 すべてインストルメンタル
[Bonus Track From Reissue CD Sanctuary CMRCD597 2002]
11. The Earle Of Salisbury [Take 4] R5 R13 T3 T10 K5
12. Transfsion [Take 2] R5 R13 K1 K4
13. Forty Eight [Take 1] R5 T10
〔楽譜掲載〕 1 G1 G2 K5、2 G11、3 G1 G2、G10、 4 G11、5 K1 K4、 7 G1 G2 K1 K4、 8 G11、9
G11 K1 K2、 1,3,7(シャナーキーから発売のCDに添付)
|
ジョン・レンボーンの最高傑作であり、スティール・ストリング・ギターの歴史に残る不滅の名盤。何度聴いても新鮮な発見があり、発表後40年以上経った現在聴いても全く古さを感じさせないのは驚異的。本作はペンタングル結成後初めてのソロアルバムで、若々しいエネルギーと溢れるような創造力に満ちている。じっくり時間をかけて多くのテイクを録音し、中からベストのものを選ぶなど、完全主義のポリシーで製作されたそうだ。タイトルがやたらと長たらしいので、日本盤には「鉄面の騎士」という邦題が付いていた。表紙はケンブリッジのトランピントン教会にあるイギリス最古の真鍮彫刻による中世の騎士の版画(イギリスの外人向け土産店でよく売っている)を何人か並べたもので、真ん中の騎士の顔だけジョンの顔写真のはめ込みというユーモラスなもの。
本作よりスタジオ録音となったため音質が飛躍的に向上。あのギブソン J-50のマホガニー・サウンドが、適度なエコーを伴って生々しくとらえられている。本作のギター・サウンドは、他の作品に比べて一層ソリッドなリズムとアグレッシブなグルーブ感があり、本作にかける彼の意気込みが感じられる。また音楽的には前作に萌芽がみられた中世音楽への傾倒が一層深まり、お得意のブルース・ジャズとの絶妙な融合に成功している。フォーク・ギタリストが、本作の様にクラシック音楽に挑戦した大胆不敵なケースは前代未聞で、そういう意味で後年のフュージョンやニューエイジ音楽の草分けと位置付けることもできる。中川イサト氏が
1970年代初め頃の紹介記事のなかで、ジョンの事を「バケモノ」と呼んでいた様に、発表当時はそれほど衝撃的だったわけで、他のギタリストに与えた影響の大きさを物語っている。
1.「The Earle Of Salisbury」はウィリアム・バードが 1611年出版したパバーヌ(宮廷の舞踏曲)で、もともとはチェンバロで弾くもの。ジョンのスタンダード・チューニングによるアレンジは一度聴いたら忘れ難く、ストレートで美しいメロディーをうまくとらえている。テリー・コックスのグロッケン(鉄琴の一種)とのデュエットで、ペンタングルの「Sweet
Child」1968 T3 では二人のライブ演奏が楽しめる。2.「The Tree They Do Grow High」は中世のバラッドで、政略結婚のためにまだ幼い男の子の妻になった娘の話。その後彼は夭折し、彼との間にできた子供に人生を託すという内容。ここではギター、フルートによるアンサンブルで、ギターは伴奏といいながら物凄くアグレッシブ。ベース音でメロディーを刻むピッキングが素晴らしく、そのリズムの乗りは生気に溢れている。彼にとってブリティッシュ・バラッド最初の録音だ。3.「Lady
Goes To Church」は、ドロップドD・チューニングによる中世風のストイックな曲。スティール弦のメタリックな響きが厳かで崇高な感じ。ナイロン弦のクラシックギターにはない透明感溢れるサウンドだ。対位法の勉強の成果が顕著に出た佳曲であるが、弾きこなすには大変な努力が必要。ジョン自身もこの様な曲は難しすぎてステージでは演らないと言っていたので、正直言ってホッとした。4.「Morgana」はレコーダーとパーカッションとのアンサンブル。中世のダンス音楽をイメージしたもので、後のジョン・レンバーン・グループの原点となる曲。
B面の最初の曲 5.「Transfusion」は目が覚める様なジャズ・ブルースの名作。作曲者のチャールズ・ロイドは確かバップ系のジャズ・サックス奏者。本曲はドラム奏者のチコ・ハミルトンのレコードからアレンジしたそうだ。ジョンの演奏には大変なエネルギーが感じられ、何度聴いても迫力とドライブ感に圧倒される。7.「My Dear Boy」も彼自身の作曲によるジャズ・ブルースでカッコイイ事この上もない。デイヴィー・グラハムからの影響を彼なりに消化し切った独自の世界を確立している。リズム・アンド・ブルースの巨人ブッカー・T・ジョーンズによる名曲9.「Sweet Potato」のリズムの乗りも素晴らしい。間奏はインプロヴィゼイションでその後のステージ等での再録音では、その都度全く異なる演奏が聴ける。また5. 9.におけるテリー・コックスのコンガは繊細極まりない素晴らしい伴奏だ。
6. 8.は中世音楽風のテーマからスタートして、途中で雰囲気が一変、ジャズ・ブルースの乗りとなる。そして最後また静かなテーマに戻るというクロスオーバー作品。いつ聴いてもハッとする新鮮味があり聞き飽きない。6.「Forty-Eight」のテリーのグロッケン、コンガは生き物のように生き生きとしている。8.「White
Fishes」はフルートのレイ・ワーリーとの共演。特に8.のイントロにおける耽美的なギター、フルートのテーマのメランコリーな響き、そして間奏部分のジャズ乗りの展開が鮮やかで、アンサンブル作品の傑作だ。ちなみにレイはバート・ヤンシュの「Birthday
Blues」1969 にも参加していたジャズ系のプレイヤー。最後の曲10.「Seven Up」もテリーのパーカッションとのデュエットで、緩めの変則チューニングによるドローン弦の連弾および中近東風なスケールと、洗練されたテーマとの融合が素晴らしい。
とにかく収録曲のすべてが名作・名演で、1曲として手を抜いたものはない。本作はギタリストとして、そのエネルギーと創造性の頂点にあった頃の作品である。本作は発売後もずっと数多くの人から愛され、ウィンダムヒルやシャナーキー等から何度も再発されており、今後も人々を魅了し続けるであろう。
[2002年サンクチュアリー・レコードから発売されたCD再発盤について]
ここにはボーナストラックとして3曲の別テイクが収録された。過去30年間、何回も繰り返し聴いてそのメロディーを覚えてしまった曲に、ある日突然別の世界が開けるのは不思議な気がする。まるでずっと昔から行き止まりだった道が、ある日壁が取り払われて先の景色が開けたかのようだ。11.「The Earle Of Salisbury」は録音された5テイクのうちテイク4( 1.はテイク5)。楽譜通りにきっちり弾く曲なので、インプロヴィゼイションの余地はなく演奏自体はほとんど同じだが、息遣いや弦に触れるタッチが微妙に異なり、聞いているとギクリとする。12.「Transfsion」(テイク2、採用された 5.は最後に録音されたテイク5)は、テーマに続く展開部分が全く違っていて、楽譜通りに演奏していては決して出せない自由な世界が広がっている。ただでさえ凄まじい演奏なのに、これをインプロヴィゼイションで演っていたとは本当にバケモノだ。13.「Forty Eight」はテイク1で、13のテイクが録音されたそうだ(そのうちテイク7が 6.として収録)。この曲もブルージーな中盤部分は別曲といえるほど異なり、当時の彼がいかにアイデアと創意に溢れていたか分かる。お馴染みのコリン・ハーパー氏の解説、マスターテープの箱写真など、おまけも沢山だ。
|
| R6 The Lady And The Unicorn (1970) Transatlantic Records TRA224 |
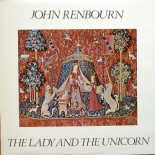 |
John Renbourn: Guitar
Terry Cox: Hand-Drum, Glockenspiel (2)
Don Harper: Viola (8)
Lee Nicholson: Concertina (5)
Tony Roberts: Flute (8)
Ray Warleigh: Flute (3,4)
Dave Swarbrick: Violin (3,4)
Bill Leader: Producer
[Side A]
1. a Trotto [Anon.] V2 V7 K5
b Saltarrello [Anon.] K5
2. a Lamento di Tristan [Anon.]
b La Rotta [Anon.] T3 T10
3. a Veri Floris [Anon.]
b Triple Ballade [Guillaume de Machaut]
4. a Bransle Gay [Claude Gervaise] T3 T10 K1
b Bransle de Bourgoyne [Claude Gervaise]
5. a Alman [Anon.]
b Melancholy Galliard [Dowland]
6. Sarabande [J. S. Bach] R28 T12
[Side B]
7. The Lady And The Unicorn
8. a My Johnny Was A Shoemaker [Trad.] R10 R12 R27 V1 V9
b Westeron Wynde [Trad.] R12
c Scarborough Fair [Trad.]
〔楽譜掲載〕1a G1 G2 G8 K5、 1b, 2ab, 4b, 5ab, 8b G1 G2 G8、 3ab G8、4a G1 G2 G8
K1 F1 F3、 7 G1 G2、 8c G1 G11、 1,2,4a,5a,7,8b (シャナーキー発売のCDに添付)
すべてインストルメンタル
レンボーン自身による曲についての簡単な解説付き
|
前作がジャズ・ブルースと中世音楽との融合をめざしたアグレッシブで野心的な「陽」の作品とすると、本作は中世音楽に没頭した耽美的な「陰」の作品。表紙のユニコーン(一角獣)は想像上の動物で、その形から性的な意味を持っている。すなわち乙女の純潔を護るものとして、またユニコーンを伴うことで純潔そのものを象徴するという。この概念は恐らくキリスト教以前の原始宗教の名残ではないかと言われている。本作のジャケットに使用された図柄は、15世紀後半に作成された6枚組の巨大なタペストリー(つづれ織り)のひとつで、パリのクリュニー中世美術館で観ることができる。最初の5枚は、乙女の仕草から味覚、聴覚、視覚、嗅覚、触覚という人間の5感を表しているという。そして本作のジャケットに使用された最後の1枚には、乙女が身につけていた貴金属や宝石を侍女が持つ宝石箱に戻す様が描かれ、天蓋には「A
Mon Seul Desir (私の唯一の望みに)」とある。これは乙女が先の5感により引き起こされた欲求や情念を放棄し、清い心に高める自らの意志を象徴するものと解釈されている。この作品が作られた中世の時代において、このような哲学的で深淵な精神世界があったとは驚きだ。本作もこの図案にふさわしい純粋で静謐な音楽世界。何度聴いても心が安らぐ作品である。
1.は変則チューニングによるシンプルなダンス・チューン。14世紀のイタリアのダンス曲で、前半のa.「Trotto」は大英博物館所蔵の楽譜から採集したもの。独特のスケールと、オープン弦によるシタールの様なドローン・サウンドが印象的。発表当時はとても奇異な感じがしたが、その後のケルト音楽の流行で慣れたせいか、今では自然に聞けるのが面白い。2.は14世紀北イタリアのダンス曲のアレンジ。a.「Lamento
di Tristan」はシタール、パーカッションとのアンサンブルでゆったりしたテンポの舞曲。バート・ヤンシュが、ソロ「Leather Launderette」1988
の「Knight's Move」で同じメロディーを使用している。b.「La Rotta」はアップテンポで、テリー・コックスのグロッケンとの共演による、はらはらと舞い落ちるような細かなピッキングが本当に素晴らしいアレンジ。ちなみに後年の「The
Maid In Bedlam」1977 R10 の「John Barleycorn」の間奏部分で本曲のモチーフが引用される。3.a.「Veri
Floris」 b.「Triple Ballade」と4b 「Bransle de Bourgoyne」はバイオリン、フルートとの共演。4.のa.「Bransle
Gay」はギター・ソロによるアップテンポで明るめのダンス・テューン。5a.「Alman」 b.「Melancholy Galliard」はコンサーティナ(タンゴ音楽のバンドネオンのようなボタン式の楽器で、アイルランド音楽でよく使用され、ピアニカみたいな音がする)とのデュエット。6.「Sarabande」はトレモロ(おそらくフェンダーのツイン・リバーブのギター・アンプ)処理を施したエレキ・ギター(愛用のギブソンESS-335)によるソロ演奏で、原曲はJ・S・バッハによる無伴奏バルティータ1番
BWV1002 の1曲。アレンジはクラシックギターの巨匠アンドレ・セゴビアによるもので、クラシックギターのピース楽譜(1曲だけの楽譜、ただしタブ譜ではない)で入手可能。2003年に
サンクチュアリから再発されたCDでは、音質および透明度の向上が著しく、エレキ・ギターを弾く際のアンプを通す前の生の音までもしっかり聞こえる。
B面最初のタイトル曲7.「The Lady And The Unicorn」はスタンダード・チューニングによる対位法の曲として最高の名曲。ギター1本でつづる音のタペストリーとも言え、その自然な流れに思わず引き込まれてしまう。音使いそのものはシンプルなので比較的弾き易くみえるが、実際マスターするのはなかなか難しい。8a
「My Johnny Was A Shoemaker」は「Sir John Alot ...」R4 の「The Tree They Do Grow
High」と同じ雰囲気のアンサンブル曲で、これも有名なトラッド。デイブ・サワーブリック(スティールアイ・スパンのメンバーで、マーティン・カーシーとのデュエットでも有名)のバイオリンとトニー・ロバーツのフルートの演奏が丁寧でとてもいい感じ。後にジョン・レンボーン・グループの「A
Maid In Bedlam」R9 では歌付のバージョンで録音される。8b 「Westeron Wynde」は16世紀頃の発祥で 2台のギターの多重録音によるアレンジ。前半はハーモニックスだけによる演奏。8c
「Scarborough Fair」はサイモンとガーファンクルでお馴染みの曲。当時マーティン・カーシー等のイギリスのフォーク・ミュージシャンがトラッドとして演奏していたもので、イギリス滞在中のポール・サイモンがこの曲を習って、アメリカ帰国後に著作権登録してしまったのは有名なエピソード。ボブ・ディランの名曲「Girl
From The North Country」の歌詞も同様である。ここではインストルメンタルとして、途中にインプロヴィゼイションを入れてじっくり演奏される。ジョンのギターは控えめであるが印象的。彼の楽譜集
G3 には本曲の歌付きのバージョンが掲載されている。
本作は、地味ではあるが上品な香り高い名作。中世の音楽を演奏しながら、ブルースやジャズの香り付けがされ、クラシック音楽の奏者とは全く異なる演奏であり、後のニュー・エイジ音楽の先駆けとも位置付けられ、ウィンダムヒル、シャナーキー他多くのレーベルから再発され、いまも多くの人々に愛されている。
2003年にサンクチュアリから発売された再発盤(CMRCD625)には「My Johnny Was A Shoemaker」と「Three Dances」の2曲がボーナストラックとして追加収録された。前者はジャッキー・マクシーのボーカル付バージョンで、1977年の「A
Maid In Bedlam」 R9と同一録音。後者は4a、2bとR4収録の「The Earle Of Salisbury」の3つのダンス曲のメドレーであるが、これも1968年
T3のライブ録音と同じ音源であり、いずれも既発表済のものである。
2005年7月29日 6.「Sarabande」の原曲の記載につき修正しました。メールをいただいたUさん、ありがとうございました。
2009年2月 ジャケット図案について追記しました。
2013年1月 パリのクリュニー中世美術館が所蔵する上記6枚のタペストリーが、2013年4月〜7月、六本木の国立新美術館で「貴婦人と一角獣展」で日本初公開されました。見に行きましたが、それは素晴らしかったです。
|
| R7 Faro Annie(1971) Transatlantic Records TRA247 |
 |
John Renbourn:Guitar, Sitar, Harmonica, Vocal
Danny Thompson: Bass (5,10)
Terry Cox :Drums (5,10)
Sue Draheim :Fiddle (4,6,9)
Pete Dyer :Harmonica (3,8)
Dorris Henderson :Chorus (1,3,11)
Bill Leader : Producer
Nic Kinsey :Engineer
Janet Kerr, Shepard Sherbell :Photo
John Ashcroft : Sleeve Design
[Side A]
1. White House Blues [Trad.] V2 V7 K2
2. Buffalo Skinners [Trad.]
3. Kokomo Blues [Trad.] R12 R13 R27 V5 V9
4. Little Sadie [Trad.]
5. Shake Shake Mamma [Trad.]
[Side B]
6. Willy O'Winsbury [Trad.] R12 T7 T11 T12 T16
7. The Cuckoo [Trad.] T4 T9
8. Come On In My Kitchen [Robert Johnson]
9. Country Blues [Trad.] T10
10. Faro Annie * [Renbourn, Cox, Thompson, Draheim]
11. Back On The Road Again [Ian A.Campbell]
〔楽譜掲載〕 1 K2 G3、 6 G3 G11
|
「Sir John Alot Of... 」1968 R5、「The Lady And The Unicorn」 1970 R6という中世音楽に傾倒した名盤2作の後に発表した作品であるが、今回はブルースやアメリカン・トラディショナル音楽がテーマ。しかも1曲を除き全て歌ものでギターはあまり目立たない。メンバーはテリー・コックス、ダニー・トンプソンというペンタングルの仲間の他、後のジョン・レンボーン・グループのオリジナル・メンバーとなるスー・ドレハイム(フィドル)等が参加している。そして興味深いのはドリス・ヘンダーソン(ボーカル)のゲスト参加。彼女はジョンのプロ・デビュー「There
You Go」 1965 R2でパートナーだった黒人歌手。そういう意味で本作は彼のルーツを掘り下げた、プライベートな雰囲気のする作品。ジャケット写真もギターを抱えて街角にしゃがみこむ彼のポートレイトでそのおだやかな表情が印象的。持っているギターは、ディック・ナイトというイギリスのルシアーの製作によるもの。
1.「White House Blues」は1901年9月6日第25代米国大統領マッキンレーの暗殺事件を題材としたバラッドで、ステージで好んで演奏される。すさまじいスピードのスリー・フィンガーのギター伴奏はとんがっていてスゴイ。それに対するジョンのボーカルはソフトで優しく、その対比が面白い。バックでドリス・ヘンダーソンのボーカルが聴ける。2.「Buffalo
Skinners」、 7.「The Cuckoo」はアメリカのトラッドで、バンジョーのフレイリング奏法の様なギター演奏。シタールによるオブリガードが良い効果をあげており、特に7.はかなりアグレッシブな演奏。3.「Kokomo
Blues」はフォーク・ブルースの名曲で、ジョンのギターは当時流行のファンク音楽に近い乗りの演奏でとても面白い出来。本作のなかでは特に際立ったギター演奏が楽しめる。ワウワウのエレキ・ギターやドリスのバック・ボーカルも入り、にぎやかな仕上がり。なおこの曲のタブ譜がジョンのホームページで公開された。4.「Little
Sadie」はアメリカに伝わる古いトラッドでフィドルが活躍。恋のもつれで相手を殺してしまい、捕まって裁かれる男のバラード。なおボブ・ディランも「Self
Portrait」で本曲を取り上げていた。5.「Shake Shake Mamma」はR&B調のアレンジがカッコイイ。
6.「Willy O'Winsbury」は本作唯一のブリティッシュ・トラッド。ペンタングルの「Solomon's Seal」 1972 T7ではジャッキーのボーカルによる演奏でしたね。ジョンの不器用なボーカルもなかなかいいものです。本曲を聴いて気に入ったエド・ガーハードは、1996年の「Counting
The Ways」でインストルメンタルとしてカバーしている。8.「Come On In My Kitchen」はロバート・ジョンソン作曲によるブルースの名作。ハーモニカやスライド・ギターが聴ける。9.「Country
Blues」はドック・ワトソンのカバーで有名なオールド・タイミーで、バンジョーを思わせるサウンド。最近ではバート・ヤンシュのドキュメンタリー映画のサントラ盤「Acoustic
Routes」1993 でビリー・コノリーがバンジョーを弾きながら歌っていた。10.「Faro Annie」は本作唯一のインストルメンタルだが、リズム・セクション、ワウワウをきかせたエレキ・ギター、ハーモニカによるリズム・アンド・ブルースのジャム・セッションのような曲。もうちょっと長くやってほしかったな。最後の曲
11.「Back On The Road Again」もバート・ヤンシュが「It Don't Bother Me」1965 でカバーした「So
Long」と同じ作者、アレックス・キャンベルによるR&B風の曲で、エレキ・ギターとリズム・セクション、そしてドリスのバックボーカルが加わった演奏。
本作は、ギンギンのブルースをやっているわけでもなく、アコースティック・ギターが目立っているわけでもないので、他の作品に比べて印象が薄いが、淡々とした演奏はそれなりの味わいがある。
[2017年12月追記]
2017年 Cherry Red Recordsから発売されたペンタングルのボックスセット「The Albums」に、同アルバムから3、5、10、11の4曲が収録されました。
|
| R8 Lost Sessions (1996) Edsel Records EDCD 490 |
 |
John Renbourn : Guitar & Vocal
Tony Roberts : Flute, Recorder
Sue Draheim : Fiddle
Claire Denise : Cello
Gordon Huntley : Pedal Steel Guitar
Lea Nicholson : Concertina
Roy Babbington : 6 String E. Bass
Terry Cox : Drums
Keshav Sathe : Tabla
Jacqui McShee : Chorus
Nic Kinsey : Engineer
1. Just Like Me
2. Sleepy John
3. Riverboat Song
4. Green Willow
5. Seven Sleepers
6. To Glastonbury R12 R17 Q15
7. Floating Stone
8. O Death
9. The Young Man's Song
〔楽譜掲載〕 5. を除く全曲 G3
レンボーン本人による解説・歌詞付き
1973年録音
|
1996年はレンボーン・ファンにとって実りの多い年であった。ひとつはTAB から発売されたビデオ「Rare Performance 1965-1995」V7
で、彼の初期およびペンタングルの映像が観れたこと。もうひとつのビッグ・ニュースは本作品の発掘である。私は事前の発売予告を全く知らなかったので、HMVで本作品を見つけた時の驚きと胸のときめきは例えようもなく、家に飛んで帰って胸をワクワクさせて聴いたものだ。私にとってはもう20年越しの満たされぬ恋が実ったようなもの。タイムカプセルの素敵な贈物だ。なぜならば、この録音こそが以前からインタビュー等で存在が言及されながら、今まで日の目を見ることなくマスターテープも紛失したと噂されていた作品で、1974年発売された彼の楽譜集「The
Guitar Of John Renbourn」 G3 にほぼ全曲が掲載されながら未発表であった幻の作品群なのである。
当時のレンボーンはペンタングルの突然の解散による契約問題のために思うようにレコードを出せなかった時期で、レンボーンの解説では自分を励ますために仲間と私的に録音したもので、公式発表する意図のないものであったというが、別の記事ではワーナー・ブラザースのために録音されたが契約問題でお蔵になったともある。録音直後にレンボーンはロンドンから抜け出し田舎に引っ越したが、その際のごたごたでマスター・テープが所在不明になったらしい。1973年録音という資料があった。
メンバーはテリー・コックスとジャッキー・マクシーのペンタングルの仲間、ケシャヴ・サテとスー・ドレハイム、トニー・ロバーツといった後のジョン・レンボーン・グループの面々という興味深いもの。ただし本作のサウンドは前後いずれの作品とも異なり、まさにペンタングルとジョン・レンボーン・グループをつなぐ「失われた環」。すべての作品がジョンのオリジナルでトラッド臭さはほとんどなく、当時のシンガー・アンド・ソングライターの音作りである。ギターは控えめで、彼のアコギを期待して買うとはずれるかもしれない。アンサンブルの一部としてのエレキ・ギターは、かなりフィーチャーされている。敢えて言うと、ペンタングルの作品「Reflection」1971T6
に収録されていたジョンのオリジナル「So Clear」に近いサウンドで、この曲が大好きな私には、レンボーンの少し頼り無いが誠実そうなボーカルを中心とした本作は、法悦の一品。
1.「Just Like Me」はレンボーンのアコギの伴奏とエレキによるリードギターが良い。当時のコンテンポラリー・フォーク風のサウンドは感涙もの。本作のブックレットには歌詞が掲載されており、ファンには大変有り難い。2.「Sleepy
John」はペダル・スティール・ギターがフィーチャーされ、ドラムスとベースのコンビネーション等、当時のジェームス・テイラー、日本の小坂忠の名作「ありがとう」やはっぴいえんどを思わせるサウンド。歌詞の内容は極めて個人的。3.「Riverboat
Song」はロンドンのテムズ川に浮かぶボートに住んだ経験を歌ったもので「Faro Annie」 1971 R7 のジャケット・ライナー等にもそれを思わせる記述がある。ペンタングルの活動による消耗とその後の契約問題に悩まされた彼のなにものにも束縛されない自由な生き様に対する渇望が感じられる。スー・ドレハイムのフィドルの素朴なサウンドが魅力的。4.「Green
Willow」は変わったサウンドの面白い曲。ワウワウのエレキギターのモコモコしたサウンドとシンバルのリズムが不思議な効果をあげ、トニー・ロバーツのフルートが洗練されたソロをとる。5.「Seven
Sleepers」はペダル・スティール・ギターが流れる、キリストの聖杯についての難解な歌。6.「To Glastonbury」は目が覚めるような鮮やかなアコギのイントロからタブラとシタール、フルートが加わる。インド音楽というよりもジャズ的な音作りで曲自体は現代的。後のジョン・レンボーン・グループとも異なるファンタスティックなサウンドが展開される。この曲はジョンのお気に入りだったようで、後年
Q15でインスト版が、またR17にソロ・バージョンが再録音された。8.「O Death」は死をテーマとしたエキセントリックな曲。チェロとリコーダーがサポートする。9.「The
Young Man's Song」は 6.と同じ雰囲気のサウンド。ここでのアコースティック・ギターのパートは「Rare Performances
1965-1995」V7 収録の1974年の映像「Rosslyn」のイントロ部分によく似ている。
|
| R9 The Hermit (1976)Transatlantic Records TRA336 |

 |
John Renbourn: Guitar
Dominique Trepeau: Guitar (6)
John James: Guitar (11)
Bob Franks: Art Direction
Paul Ellis: Illustration
Paul Chave: Design
[Side A]
1. The Hermit
2. John's Tune [James, Renbourn]
3. Goat Island
4. Old Mac Bladgitt
5. Faro's Rag
6. Caroline's Tune [Trepeau]
[Side B]
7. Three Pieces By O'Carolan [O'Carolan]
a. The Lamentation Of Owen Roe O'Neill R13 R20 R24 R27 V5 V7 K3
b. Lord Inchiquin
c. Mrs. Power (O'Carolan's Concerto)
8. The Princess And The Puddings R21
9. Bicycle Tune
10. Pavanna (Annna Bannana)
11. Medley
a. A Toye [Thomas Robinson]
b. Lord Willoughby's Welcome Home [Robinson, Vallet]
〔楽譜掲載〕 1 G4 G5 G10、F3, 5 G4 G5 F3、 2,4,10 G4 G5、3 G4 G5 F4、 7 G4 F3 F5、
8 G1 G2、 9 G4、G5、G10、11 G8
レンボーン本人による各曲の解説付き
すべてインストルメンタル
写真上 : オリジナル・ジャケットデザイン
写真下 : 米国Shanachie盤のジャケットデザイン
|
その後のフィンガースタイル・ギターの方向性を決定した記念碑的作品。ペンタングル解散に係る契約上のトラブル等による長い沈黙の後に発表された作品で、発売時喜んで買った事を思い出す。当時はキング・クリムゾン等のプログレッシヴ・ロックやオールマン・ブラザース・バンド等のヘビーなロックを愛好していた時代でもあり、2曲のデュエットを除きすべてギター・ソロという内容にちょっと寂しいなと思ったのだ。そしてケルト音楽に接した経験がなかったため、かなり違和感を感じた記憶がある。通常のクラシック音楽との区別もはっきりできず、レンボーンはクラシックに走るのかなぁと、彼のブルースとジャズの作品が好きだった私は不安になったのだ。しかし、いつの間にか愛聴盤になったようで、1979年3月の来日コンサート会場で本作のジャケット裏面にサインを貰ったりして、個人的に愛着のある作品。発表後20年経過した時点で聴くと、その後色々な音楽に慣れ親しんだせいか、当時と全く異なる印象を持つことが感慨深い。それだけ時代の先を行っていた作品だったのだ。アレックス・ド・グラッシ、ピエール・ベンスーザンをはじめ多くのギタリストに大きな影響を与えており、ダグ・スミスは本作を聴いてクラシックから転向したと言っている。中世、ケルト音楽に取り組んだといっても、底流の感覚と精神は非常に現代的かつ理知的である。ただし和声やリズムの使い方等で、最近のギタリストの作品の方がはるかに洗練されていると思うが、本作の持つ輝きは全く褪せない。
タイトル曲の1.「The Hermit」は、フィンガースタイルの将来を先取りした作品。ハーモニクスの効果的な使用、ドロップド・D・チューニング(DADGBE)
の響き、流れるような奏法が当時新鮮だった。タイトルの「世捨て人」は、当時南デーヴォンで暮らしていたという彼自身のようだ。2.「John's Tune」はジョン・ジェイムスの名曲「Head
In The Clouds」のテーマをレンボーン風に発展させたもの。ちなみにレンボーンが3曲ゲスト参加した1975年発表の同名のアルバム Q13
は傑作なので是非聴いてほしい。本曲のチューニングがDADGBEであるのに対し、ジェイムスのバージョンはスタンダード・チューニング。本作から変則チュニングの使用が本格化しており、3.「Goat
Island」も1.と同傾向の曲でDAEGBEという変わったチューニングを使用している。4.「Old Mac Bladgitt」は DGDGBD
を使いながらキーがGメイジャーでない不思議な曲。美しく瞑想感ある私の大好きな曲。5.「Faro's Rag」は当時のラグタイム・ギター全盛の流行に対するレンボーンの回答か。ラグタイムと言ってもちゃんと彼の音に消化し切っているところがスゴイ。低音の動きはレンボーンの独壇場。6.「Caroline's
Tune」はフランスのギタリストが来訪した時に録音したというが、ドミニク・トレポーという人については不明。レンボーンはリード・ギターを担当。
7.「Three Pieces By O'Carolan」はアイルランドの伝説的なハーピスト、オカロランの作品。今でこそ多くのギタリストがレパートリーにしているけど、私がオカロランの作品を聴いたのは本作が初めてだった。8.「The
Princess And The Puddings」は45秒のお菓子のCM曲を改作したもので、対位法による今までの作品に近い内容。9.「Bicycle
Tune」は何故か初版レコードの裏ジャケットに曲名が表示されていない。EADF#BE というチューニングによりリュートの様な響きをだした名曲。10.「Pavanna」も比較的オーソドックスな奏法による中世音楽。11.のメドレーはジョン・ジェイムスとのデュエット曲。エリザベス朝時代に流行した曲で、レンボーンとジェイムスが交互にリードをとって、メロディーの掛け合いをする。なお本作のレコード盤での表紙は「Hermit(世捨て人)」の印象的なイラストであったがシャナーキーからの再発CDはレンボーンの演奏風景に変わったが、その後の再発はオリジナル・デザインに戻った。ちなみに本作の使用ギターはギルドの
D55(ドレッドノート・サイズのハカランダ・ボディ)。以前読んだジョンのインタビュー記事で、ギブソンJ-50はこの作品まで使われたとあったが、レコードで聴く限り、マホガニー・ボディ系の抜けのよい明るい音ではなく、硬質でダークなローズウッドの響きなので、ギルドが正しいと思う(一部の曲でギブソンを使っているのかもしれない)。
2004年サンクチュアリよりオリジナルジャケットにてリイシューされ、そこには以下5曲のボーナストラックが収録されている。未発表曲はなく、ジャケットの曲目が以下のとおり誤って表示されてたので要注意だ。
トラック番号 曲名 共演者 オリジナル収録作
誤 正
14 12. Luke’s Little Summer ソロ R11 1978
12 13. Luckett Sunday ソロ R11 1978
15 14. Minuet In D Minor ステファングロスマン R22 1986
13 15. New Nothynge ジョン・ジェイムス Q13 1977
16 16. From The Bridge ジョン・ジェイムス Q13 1977
レコード会社のホームページでは、当時再発されていなかった「The Guitar Of John Renbourn」Q15 1977 から数曲のウルトラレア曲が収録されると発表されていたが、アマゾンから届いたCDには、残念ながら入っていなかった。でも上記15.
16あたりも未CD化の傑作レア曲だったので、まあよしとするか。
|
| R10 A Maid In Bedlam (1977) Transatlantic Records TRA348 |
 |
John Renbourn: Guitar, Vocal
Jacqui McShee: Vocal
Tony Roberts: Flute, Recorder, Oboe, Piccolo, Vocal
Sue Draheim: Fiddle, Vocal
Keshave Sathe: Tabla, Finger Cymbals
Nick Kinsey: Engineer
Peter Smith: Photo
Graves/Aslett Assoc.Ltd: Design
[Side A]
1. Blackwaterside
2. a Nacht Tanz *
b Shaeffertanz * [Susato]
3. A Maid In Bedlam R12
4. a Gypsy Dance * R12 R13
b Jews Dance * [Hans Neusidler] R12 R13
5. John Barleycorn R10 R12 R13 R19 V1
[Side B]
6. Reynardine
7. My Johnny Was A Shoemaker R6 R10 R12 R27 V1 V9
8. Death And The Lady R12
9. a The Battle Of Augrham *
b In A Line* [Renbourn, Roberts, Draheim,Sathe]
10. Talk About Suffering
〔楽譜掲載〕 4 G8、 6 G3
|
ペンタングル解散後のレンボーンが前作「Hermit」R8に続いて発表したトラッドの薫り高いアンサンブル集。「The Lady And The
Unicorn」1970 R6 以来の仲間でその後も長くパートナーとして活躍するマルチ・リード奏者のトニー・ロバーツ、アメリカ人フィドル奏者スー・ドレハイム(1949-2013
「Faro Annie」R7や「Lost Sessions」R8 にも参加。レンボーンによると、1996年 4月の時点で彼女はアメリカ・カリフォルニア州のサンタ・ローザ・オーケストラ在籍とのこと。その後もクラシック、トラディショナル・ミュージックのジャンルにて活躍し、2013年没)、ビートルズにインド音楽を教えた仲間とインド音楽とジャズのフュージョン・グループを組んでいたタブラ(インド独特の打楽器)奏者のケシャヴ・サテ
(1928-2012) 、そしてペンタングルの仲間であるボーカルのジャッキー・マクシーからなるグループ。トラッド中心のレパートリーでジョンのギターはアンサンブルの一員として控えめ。しかもインド音楽のタブラの使用は当時賛否両論で、特に保守的なトラッド支持者は批判的であった。確かにタブラの音は独特のクセがあり、慣れるまで少し時間がかかるかもしれない。私はギタリストのラルフ・タウナーが在籍するアメリカのジャズ・グループ、オレゴンが大好きで、そのパーカッショニストであったコリン・ウォルコットが同じタブラの名人であり、そういう意味で大好きな両者が意外なところで結びついたため、大喜びしたことを覚えている。格調高いジャケット・デザイン、タイトル曲の恋に狂った美しい女性のイラストが秀逸。これはイギリスの画家・詩人ロセッティ(1828-1882)の作品「ラ・ピア・デ・トロメイ」(カンサス大学付属スペンサー美術館所蔵))の女性の姿のみを抜き出してコラージュしたもの。ちなみにこの女性は、ロセッティが生涯にわたり思いを寄せたと言われるウィリアム・モリス(デザイナー、思想家)の妻ジェーン・バーデンがモデルである。
1.「Blackwaterside」はバート・ヤンシュのソロ「Jack Orion」1966 やアン・ブリッグスで名高い曲で、ジャッキーと(恐らく)スーのハーモニー・ボーカル、トニーのレコーダーとスーのフィドルのユニゾン演奏がとても印象的な曲。男に騙され捨てられた女の悲しみを歌ったトラッドで、ブラックウォーターはアイルランドの川の名前。2.の前半「Nacht
Tanz」はドイツ語で「夜のダンス」という意味。中世ダンス音楽風で、ジョンのギター、トニーのオーボエ、ケシャヴェのタブラによる摩訶不思議なサウンド。3.「A
Maid In Bedlam」の「Bedlam」とはロンドンのベツレヘム病院のことで、16世紀からは精神病院になった。本曲は恋するあまり気が狂った娘の悲劇を歌ったトラッド。4.「a
Gypsy Dance b Jews Dance」は優雅なダンス・テューンで16世紀に活躍したドイツのリュート奏者ハンス・ニューシエドラーの作品。5.「John
Barleycornは非常に有名なトラッドで、スティヴィー・ウィンウッド率いるイギリスのロック・グループ、トラフィックが取り上げてアルバムのタイトルにしたことで有名。大麦からビールが作られる過程を、死(麦)と変身による再生(ビール)に比喩して、ジョン・バレイコンという名の擬人法で語ったバラッドで、宗教的なものが根底にある。女性2人、男性2人による輪唱形式のボーカルが素晴らしい。間奏で流れるメロディーは「The
Lady And The Unicorn」1970 R6に収録されていたインスト曲「La Rotta」と同じもので、思わずニヤッとしてしまう。
6.「Reynardine」は有名なトラッドで、バート・ヤンシュもソロ・アルバム「Rosemary Lane」1971や後期ペンタングルの「So
Early In The Spring」1988 で取り上げていたもの。この歌の主人公はキツネの恰好をした魔物で、若い女性をさらう悪者とされているが、アイルランドでは正義の英雄とされており、トラッド独特のダブル・ミーニングを持つ奥深い歌。7.「My
Johnny Was A Shoemaker」は「The Lady And The Unicorn」R5 のバージョンとは異なり、ジャッキーのボーカル付き。背後で聞こえるギター、フィドル、フルートのアンサンブルが素晴らしい。8.「Death
And The Lady」は男性2人と女性2人の掛け合いによるボーカルで、死神のことを歌ったトラッド。お迎えに来た死神の前にはいかなる権力も富も無力であり運命に逆らえない定めを歌う。9.の前半「The
Battle Of Augrham」は典型的なアイリッシュ・フィドル・チューンのメロディーで、スーのフィドルとトニーのフルートのユニゾンが大活躍する。後半は本作唯一のオリジナルで、ジョンの弾くエレキギターの和声が現代的で、メンバーの素晴らしい集団演奏が聴ける。10.「Talk
About Suffering」はドック・ワトソンの無伴奏の歌が有名なスピリチャル・ソングで、グループによるアカペラ・ボーカル(厳密にはフィドルの音が少し入っているが)で厳かに終わる。
|
| R11 John Renbourn & Stefan Grossman (1978) Kicking Mule SNKF1398 |
 |
John Renbourn & Stefan Grossman
John Renbourn:Guitar (Solo 4, 8)
Stefan Grossman: Guitar (Solo 2, 10)
Nic Kinsey : Enginneer
Roger Perry : Photo
Terry Eden : Cover Design
Karl Dallas : Liner Notes
[Side A]
1. Snap A Little Owl [enbourn, Grossman]
2. Bermuda Triangle Exit [Grossman]
3. Theme From Charles Mingus' The Shoes Of The Fisherman's Wife Are Some
Jive Ass Slippers [C.Mingus] R20 V2
4. Luckett Sunday (Renbourn)
5. Why A Duck [Grossman]
6. The Drifter [Renbourn] Q15
[Side B]
7. Looper's Corner [Grossman] R20 V2 V4
8. Luke's Little Summer [Renbourn]
9. Spirit Levels [Renbourn, Grossman] R20 Q15 Q15 V2 V3 V4
10. The Way She Walks [Grossman]
11. Woman From Donori [Grossman]
〔楽譜掲載〕1,5,6,7,11 G7、 4,8 G4 G5 G10 F2、 レコードに添付されたタブ譜 (3,9以外全曲)
再発CDには、「Spirit Levels」以外のすべての収録曲のタブ譜がPDFファイルとしてディスクに収納。
注)2,10 はグロスマンのソロ(レンボーン非参加)
すべてインストルメンタル
左写真の表紙は二人のサインつき
|
ステファン・グロスマン (1945- ) とレンボーンがデュエット・アルバムを制作するという記事を読んだとき「本当?ウッソー」と我が目を疑った記憶がある。ブルースという共通項がありながら、グロスマンはカントリー・ブルースの教則の権威、片やレンボーンは中世音楽の世界に耽溺する芸術家という偏見があり、二人のコラボレーションのイメージが全くわかなかったからだ。とは言え、レンボーンはブルースギターの鍛錬にあたっては、グロスマンのお世話になったらしい。あるプロモーターの計らいでジョイント・コンサートを行うこととなり、一緒に演奏したところ良かったので始めたというところか。本作の制作のために十分なリハーサルを重ねたため完成まで18カ月かかったという通り、単なるチームワークの良さのみならず、互いのベストを引き出す相乗効果が希有なレベルまで昇華した傑作となった。本作は二人の来日時にサイン付きのレコードを買った懐かしい記憶もあり、数あるギター・アルバムのコレクションの中でも5指に入る愛聴盤となった。表紙は日当たりの強い屋外でギターを抱えた眩しそうな二人の写真で、当時のキッキング・ミュールお得意の人工着色(白黒写真を人工的に着色するもので、昔カラー写真がなかったころに行われた手法)のノスタルジックな感じがうまく出たもの。表紙写真で二人が抱えているギターは、いずれもシカゴのラーソン兄弟が製作したビンテージもので、グロスマンのものはユーノフォン、レンボーンのものはプレイリー・ステイトのブランドで発売されていたもの。後者はもともとアーチド・トップだったものをフラット・トップにコンバートしたものらしい。両方とも当時グロスマンが所有していたもので、キッキング・ミュール・レコードのジャケットに使用された写真には、この手のもの(グロスマンのギターを持たせて写真撮影するパターン)が多かった。
1.「Snap A Little Owl」のテーマはレンボーンの作曲と思われるが、その演奏はグロスマンが担当し、レンボーンがリードギターを付けている。せわしいフィンガーピッキングのパートは今までになかった新鮮な響きが感じられた。途中のレンボーンのリードギターは絶妙のコントロールを誇っている。以前
TAB ギタースクールで先生とのデュエットをトライしたが、とても気持ちが良かった思い出がある。2. 10.はグロスマンのソロでレンボーンは不参加。特に2.「Bermuda
Triangle Exit」はグロスマンのオリジナル作品の傑作で本作における彼の意気込みを感じることができる。本作で私のグロスマンに対する印象が一変した。長いタイトルの3.はジャズの巨匠チャーリー・ミンガス(かの「Goodbye
Porkpie Hat」の作者) の曲。タイトルは抱腹絶倒のナンセンスなものらしい。レンボーンのアレンジによる厳かなテーマからグロスマンのフラット・ピックによるインプロヴィゼイションのパートへの切り替えが鮮やか。4.「Luckett
Sunday」と8.「Luke's Little Summer」はレンボーンのソロで、モダンな音使いによる現代のクラシック・ギター探究の究極がここにある。以後のレンボーンはより一層中世音楽に傾倒してゆくので、地味であるが非常に美しく貴重な名曲。特に子供の声をイメージしたという
8.のハーモニクスの使い方が最高。
5.「Why A Duck」、7.「Looper's Corner」はグロスマンのカラーがより強く出た作品だが、レンボーンのハーモニー付けも互角に張り合っている。6.「The
Drifter」 はレンボーンの作品で、彼の奏でる複雑なアルペジオにのせてグロスマンのメロディーの演奏が光る。9.「Spirit Levels」はジャズ調のテーマ(グロスマンのリードギター)から始まり、途中で一転してグロスマンの弾くリフに乗ってジョンがソロをとるという両者のスタイルの違いをうまく取り入れた佳曲。途中のパートでグロスマンの弾くミュートロンという効果をかけた、霧の彼方から聞こえてくるような音、特に後半のボトルネック・ギターによる叫びは効果的。ちなみに6.9.は、レンボーンが業者のためのバック音楽として製作した「The
Guitar Of John Renbourn」1977 Q15に入っていた曲を焼き直したもの。9.の中盤のインプロヴィゼイション・パートは本作のために付け加えられたものだ。11.「Woman
From Donori」はグロスマンの作品で、変則チューニングでゆったりと弾くグロスマンのバックのギターがとても良い。ジョンは気持ち良さそうにハーモニーを加えていて、最後の曲として良い後味が残る。本作の成功によりこのコンビは以後長期にわたり続くこととなった。ちなみに本作の初期のバージョンにはレコード盤サイズのタブ譜が無料で添付され、3.
9.以外の全曲が掲載(ただしデュエット曲は伴奏パートのみ)された。
なお2004年にキャッスルより発売された「The Hermit」R9 の再発盤に、ボーナス・トラックとして4. 8. が収録された。
[2022年4月追記]
初期ペンタングル解散前、1972年最後のツアーの音源で、3.「Theme From Charles Mingus' The Shoes Of The Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers」の原形を演奏している曲があります(「その他音源・映像」を参照)。
|
| R12 A Maid In Bremen (2020) MIG MIG02392 CD |
 |
John Renbourn: Guitar, Vocal
Jacqui McShee: Vocal
Tony Roberts: Flute, Vocal
Sandy Spencer: Cello
Keshave Sathe: Tabla
1. I Am A Maid That's Deep In Love T5 T10 T17 V9
2. Death And The Lady R10
3. Westron Wynde R6
4. Sweet Potato R5 R20 R24 V3 V5 V7 K1 K2 *
5. John Barleycorn R10 R13 R19 V1
6. Turn Your Money Green R27 T3 T10 T15
7. My Johnny Was A Shoemaker R6 R10 R27 V1 V9
8. To Glastonbury R8 R17 Q15
9. Gypsy Dance R10 R13*
Jews Dance Neusiedler Melody R10 R13 * [Hans Neusiedler]
10. The Maid On The Shore R16 Q15 V1
11. A Maid In Bedlam R10
12. Sidi Brahim R16 R18 R19 *
13. Cruel Sister R27 T5 T17 T18
14. Kokomo Blues R7 R13 R27 V5 V9
15. Willy Of Winsbury R7 T7 T11 T12 T16
録音: 1978年2月14日 Live At Roemer, Bremen
注: 3. はジョン非参加
|
発売予告を見て、アーティストの没後に出されるいつもの発掘物かと思いましたが、フタを開けてみたらとんでもない逸品でした!
ドイツ・ブレーメンのラジオ局が、地元ナイトクラブでのライブを放送用に録音したもので、各楽器とボーカルの音の分離が良く、かつクリアに捉えられている。レーベル名の「MIG」は「Made In Germany」のことで、ジャケット裏には 「Radio
Bremen」のロゴも一緒に表示されている。同レーベルからは、1970年代の放送音源が多くCD化されているようだ。
本コンサートはジョン・レンボーン・グループ最初のアルバム「A Maid In Bedlam」1978 R10 発売の翌年ということで、オリジナルの手持ち曲が多くなかったようで、昔演っていたペンタングルやソロの曲を多く取り上げている。そのため、後に録音されたライブアルバムやビデオとはかなり異なった曲目となり、その分本録音の価値を高めている。そんな曲のひとつである 1.「I Am A Maid That's Deep In Love」は、ペンタングル時代のレパートリー で、「Cruel Sister」 1970 T5 から。ジョンのギターとジャッキーのボーカルに、トニー・ロバーツのフルートとケジャヴ・サテ(1928-2012)
のタブラが絡んでゆく様は、聴いていて最高に気持ちが良い。そして途中からサンディー・スペンサーのチェロが入るのがとても新鮮。彼女はアメリカ人で、1970年代にMormosというフランスのプログレッシブ・フォークのグループや、ウィズ・ジョーンズ、そしてジャズのトレヴァー・ワッツ等のレコードでチェロを弾いている。バイオリンのスー・ドレハイムの後任として短期間グループに加わり、その後アメリカに帰国したらしい。ジャッキーのコメントによると、彼女が参加したグループの音源はこれのみとのこと(「World
Music Central.org」の記事より)。その後彼女はケープ・コッドを本拠地とするCape Symphony Orchestraの一員として活躍する他、教育・指導に携わり、2012年1月に76歳で亡くなったという記事(「Notes
On The Arts - Arts And Entertainment On Cape Cod」より)があった。グループのファースト・アルバムに収録された 2.「Death And The Lady」は、ジョンとトニーの少し不器用な合唱、そして途中からジャッキーが加わって三重唱になってゆく様がそれなりに魅力的。3.「Westron Wynde」はジャッキーの独唱による短い曲で、ジョンは不参加。ジョンのアルバム「The Lady And Unicorn」1970 R6に同一タイトルのギター演奏曲があるが、メロディーが似ているような、似ていないような....。4.「Sweet Potato」は本CDの聴きもののひとつ。トニーのフルートとケジャヴのタブラ付きもさることながら、間奏でサンディーのチェロのソロが楽しめるのだ!ジャキーが「ビール作りの歌です」と紹介する 5.「John Barleycorn」でも、バックで鳴ってるサンディーのチェロがユニークな彩りを添えている。
ファーリー・ルイスのブルース 6.「Turn Your Money Green」は、ジョンとジャッキーのデュオによる古いレパートリで、ペンタングルの「Sweet
Child」1968 T3 のライブが初公式録音。ここでもトニーとケジャヴが加わり、より華やかな出来栄えになっている。ジャズ、ブルース、トラッド何でもこなすトニーのプレイが変幻自在で素晴らしく、サンディーもチェロでブルージーな音を出している。正統的なトラッド 7.「My Johnny Was A Shoemaker」もここでは、フルート、チェロとタブラでプログレッシブな響きを帯びている。本作で唯一のジョンの作曲による
8.「To Glastonbury」は長らく未発表だった曲で、当初は楽譜G1のみで紹介され、その後1980年の来日録音「So Early In
The Spring」 R17 で初めて公式発表され、さらに1996年に当初の録音が「Lost Sessions」R8 として発表。さらに2005年になって1977年に業者用にのみ販売されていたレコード「The
Guitar Of John Renbourn」Q15が一般向けに販売されたことで、当時ジャッキーのボーカル(但しハミングのみ)、フルート、タブラでの別録音が存在していたことが明らかになったという波乱万丈の歴史を持つ曲だ。9.「Gypsy Dance/Jews Dance Neusiedler Melody」のハンス・ニューシエドラーは、16世紀に活躍したドイツのリュート奏者。10.「The Maid On The Shore」は、後1980年に発表されるセカンド・アルバム「The Enchanted Garden」R16 に収められた他、前述の「The Guitar Of
John Renbourn」Q15 に「Portrait Of A Village」というタイトルのインストルメンタル版がある。
セカンド・アルバムに収録された傑作インスト曲 12.「Sidi Brahim」は、本作のハイライトだ。ジョンは「新曲で出来上がってから4日目、曲名はまだなく、あまり上手くはできないけど、面白い曲です」と紹介している。出来たてのほやほやが本当ならば、ここでの各メンバーの演奏力は驚異的。特にトニー・ロバーツのフルートは超人的と言ってもよい凄さだ。ジョンのギターも後の公式録音とは異なるもので面白い。そしてここでも背景に聞こえるサンディのチェロの低音がまことに効果的。粗削りであるが、素晴らしい演奏だ。 13.「Cruel Sister」も 1.と同じくペンタングルのレパートリーから。ジャッキーがオーディエンスに対し「ファラララ...」を一緒に歌うよう勧めている(でも彼らの歌声は聞こえないけどね)。ここでもフルートとタブラの絡みが新鮮。ここでコンサートはいったん終了し、アンコールになる。1971年のソロアルバム「Faro Annie」 R7が初出の 14.「Kokomo Blues」もフルート、タブラ、チェロが加わりドライブがかかったせいか、時に唸り声を挙げながら弾きまくるジョンのギター、ジョンとジャッキーのボーカルが、常に増してグルーヴィーだ。オーディエンスの熱い手拍子の後、最後に演奏される 15.「Will Of Winsbury」もペンタングル時代の曲(「Salomon's Seal」1972 T7所収)。ここではチェロとタブラの音が控えめなので、比較的大人し目の演奏になっている。
ジョン・レンボーン・グループとしては珍しい曲、珍しいメンバーによる演奏が満載で、かつ良質なサウンドで楽しめるお宝音源。
[2021年8月作成]
|
|
|
|

