Troublesome Tornado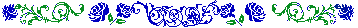 依りかくる糸 written by 梓音
依りかくる糸 written by 梓音
いつもよりは、との注釈はつくものの、早めに起きてきたハウルがマイケルと一緒に城の中の修理と魔法の準備を始めたのをソフィーはぼんやりとソファに座って見ていた。
「良いかい、マイケル。これはこちらの魔法だから順番が少し違うんだ。それを間違えないようにね。」
白墨を持って、昨日もう一つの城から得てきたらしい魔法を丁寧に教えている彼にマイケルは真剣な顔で何度も頷いている。
「ねえ、何をするつもりなの? 修理ならさっき終わったじゃない。」
点検とまだ終わっていないところを朝食が終わってすぐに直し始めたというのに今度は何をやるつもりなのかしら?
不審そうに二人を見るソフィーにハウルは移動するんだよ、とあっさりと答えた。
「移動? どうして?」
「どうしてってここじゃあいろいろ不便だからさ。それに目立ちすぎる。とにかく国境だけでも越えておかないと。」
何だかこことあっちは厄介なことをしている最中のようだしね
意味ありげに呟くとハウルはすぐにマイケルに向かっていろいろと指示を与え始めた。もっと訊こうと思っていたソフィーはそれ以上の質問をハウルがするりと避けたことに気がつき不満げに鼻を鳴らす。
「つまらないわ・・・ねえ、カルシファー?」
「おいらは寝てたいよ、ソフィー」
あいつら、この後おいらをこき使う気なんだ
嫌そうに体を揺らす火の悪魔に、そういえばと彼女は二人の様子を再度見た。ハウルもマイケルも城のあちこちを走り回って、持っている白墨で目印を書き込んでいる。その様子はいつかの引越しのようだった。
「さっき掃除が終わったばかりなのに・・・あとにすれば良かった・・・」
「あんたそれしか言うことは無いのかい?」
思わず呟いた彼女の背後から呆れた声が聞こえて振り返るとハウルが立っている。
「だって退屈なんだもの。魔法のことはあたしは判らないし、花屋の仕事も無いから気晴らしの花摘みも出来ないし。」
「だったら行き先は花のあるところにしよう、ソフィー。頼むからモップを振り回して印を消すなんてことをするんじゃないよ。」
「判ってるわよ、そんなこと。」
「ハウルさん、終わりました!」
「よし! さあカルシファー、やるよ!」
さっき教えたとおりに魔力を使ってくれ
「おいらこれが終わったら当分寝るからな!」
不服そうにゆらゆらとハウルに近づいていく火の悪魔はそれでもハウルが用意した彼の定位置に収まるとハウルの詠唱に合わせてくるくると体を回しながら青白い光を部屋中に散らばしていく。
「屋内の次元を固定しているんです。」
部屋が燃えてしまう!と悲鳴をあげそうになったソフィーのそばに近づいてきたマイケルが彼女に小さく囁いた。
「ほら、この城の中は本当はがやがや町の家でしょう? ソフィーさんが魔法をかけてくれたから上手い具合に切り離されてこっちに来てくれたけど、今のままだととても不安定なんですよ。だからハウルさんとカルシファーが一時的に城のほうに固定しているんです。」
不思議そうなソフィーにマイケルは僕も良くは判らないんですけどね、とはにかみながら説明をする。それを彼女もそういえばそうだったわと思い直した。そうよ、この城こそが見せ掛けなんですもの。
部屋のあちこちが青白く発光していくさまは日の高い時間のいまですらもとても綺麗だった。ソフィーもマイケルも黙って見つめていると、動きを止めたカルシファーがハウルを見る。
「良いみたいだよ。」
「そうだね。じゃあ次は移動だ。頼むよ、カルシファー?」
「判ってるよ。ソフィー、おいらに薪をおくれよ!」
ふわりと暖炉に戻った火の悪魔からの催促にソフィーが数本薪を投げ入れるとカルシファーは勢いよく炎を出した。ちりちりと髪が彼の魔力で音を立てる。
「ソフィーさん、見てください!」
城が浮いてますよ!
窓辺に寄ったマイケルの叫びに近づいて見るとゆっくりと遠ざかる地面が見えた。
「ここの魔法も解けちゃってるのね・・・」
いつもならがやがや町が見えるのに
「いまはどことも繋がっていないからね。あんたが普段願っているとおりの風景なんだから少しは嬉しがったら?」
悪戯っぽく囁く夫の顔を軽くはたいてソフィーは窓の外の風景に集中した。上昇するにつれて空が近くなる。山を越えるほどの高さになると、両方の国から戦闘機が飛びかっているのが見えてソフィーは心配そうにハウルを振り返った。
「ねえ、あの飛行機に見つかって撃たれちゃうなんてことないわよね?」
「大丈夫だよ、ソフィー。この城にはさっきマイケルと二人で魔法をかけたから僕たち以外には見えないし、攻撃も受けない。」
面白いものを見つけたんだ、と得意そうに手元の紙を見せる彼にソフィーは首を傾げた。見えなくて攻撃もされない? そんな便利な魔法があるの?
「だって見えなくたってあるわけでしょう? 間違って飛んできた弾に当たるってこともあるんじゃないの?」
「無いよ。この魔法は絶対防御といってあらゆる物理的攻撃も魔法攻撃も受け付けないんだ。難を言うのならこちらからも外に向けて魔法を使えないということだけどね。」
「じゃあ駄目じゃない。」
鼻を鳴らして毒づいたソフィーにマイケルはそんなことはありません!と瞳を輝かせる。花屋へと続いていた通路の一角を見てくださいと言われ、見るとそこには小さな穴が開いていた。
「ここの1点だけ魔法が掛かってないんです。苦労したんですよ、攻撃を受けにくいところを探すの。だからハウルさんが魔法を使えなくなるってことは無いんですよ!」
凄いですよね!
興奮したように話すマイケルはすっかり師の偉大さに魅了されているようで、やっぱりマイケルもいろいろと不安だったのねと彼女は溜息をついた。それにしても不思議な魔法だわ。あの飛行機なんてどうして旋回したのか判ってないんじゃないのかしら
城の眼と鼻先まで近づいて来た戦闘機がぶつかる直前に当たり前のように城を避けて大きく左に曲がったのを見た彼女はそう思う。そのまま小さくなるまで見送った彼女はハウルの呼び声に振り返ると、彼は見えてきたよ!と窓を大きく開け放した。
「まあ・・・・!」
「これなら気に入るだろう、奥さん?」
着いたら好きなだけ気晴らしをしてきなよ
吹き込んでくる風に髪を舞い上がられながらもソフィーは眼下の景色に見惚れていた。大きな山脈の向こうに広がる緑の中で色とりどりの花々が絨毯のように敷き詰められている。だんだんと近くなる光景に彼女はわくわくとしたがはっと気がついて夫を振り返った。
「ねえハウル。あそこって荒地ではないわよね?」
「違うよ。特に魔法の残り香もないしね。それに荒地なんて見えないじゃないか。」
ほらね
言われてみれば確かにその通りでソフィーはほっとする。考えすぎよね
そうこうしているうちに城は地面へと近づいていき、カルシファーの着いたよとの声にハウルが颯爽と扉に近づいたのでソフィーとマイケルも追いかけた。
「さあ、僕たちの仮の住処を見に行こう!」
「おいらは疲れたから寝てる。起こすなよ!」
ぷすぷすと弱々しげな炎を揺らす悪魔にハウルが「もちろんだよ、相棒!」とおどけて言うと指をすいっと振って彼の上に薪を2、3本落とした。ソフィーも戸棚に駆け寄ってブランデーを少しコップに注ぎいれると彼の近くの薪に浸み込ませるように垂らし、残りはカルシファーの上に少しずつ降らせていく。嬉しそうに炎を揺らめかせる悪魔に彼女はご苦労さまと微笑むと、戸口で拗ねたように待っているハウルの方へと戻っていった。
「さあ、行きましょう。ハウル」
「あんたは僕以外には優しいよね。」
僕はあんたの希望通りの場所を選んだのにさ
「そんなことは無いわ。とても素敵なところじゃない。」
不満たらたらで呟くハウルに苦笑しながら辺りをソフィーは見回した。魔法の気配は無いとのハウルの言うとおり、ここの花たちは彼が荒地で咲かせているような季節を無視した咲き方はしていない。
「綺麗ね・・・」
「気に入った、ソフィー?」
「ええ、とても。ねえ、お昼はここで食べましょう? あたしすぐに準備をしてくるから!」
嬉しそうに城へと戻っていくソフィーの後姿にあーあと残念そうな表情を浮かべながらハウルは見送る。ソフィーはすっかりこの場所が気に入ったようだった。
「素敵なところですね、ハウルさん!」
マーサにも見せてあげたいなあ
夢見るような弟子の言葉にハウルはぐるりと辺りを見回した。確かにこの花々や大地からは花の成長を助ける程度の微弱な魔法が感じられるくらいで意図的なものは感じない。けれど
「マイケル」
呼びかけると彼は無邪気になんですかと振り返る。それにハウルはすうっと一点を指差した。眼には見えないけれどもこの先には魔法を湛えた何かがある。
「あちらをちょっと見てきてくれないかな。何があるかだけを確認してくれれば良いから。」
ハウルの言葉にマイケルは駆け出して行った。それを見送って彼は昨夜消した水鏡を取り出す。鏡の中には小さな少年と年老いた老婆が何事かを話している。そうして飛び込んできた金髪の青年。
「ハウル、準備できたわよ! あら・・・・」
バスケットに食事を詰めたソフィーは昨夜から行方の気になっていた水鏡を見つけて駆け寄った。映し出されたそれに瞳を見開く。
「これがハウル? それにこのおばあちゃんはあたし・・・?」
「違うよ、ソフィー。これはこの世界の『ソフィー』だ。あんたじゃないよ。」
「ハウルさん! 見てきました! あ!」
戻ってきたマイケルも水鏡を見つけて駆け寄ってきた。水面に映る3つの人影を食い入るように見つめると困惑したように振り返る。
『マルクル、ほら』
「マルクル、ですって。」
「僕のことでしょうか・・・」
「あんたたちときたら! マイケル、ほら早く報告しなさい。ソフィーも早く準備をしてよ。これ以上僕を放ったらかしにしたらこの水鏡は見せないよ?」
それでも聞いてくれないなら緑のねばねばを出そうかな
ぼそ、と呟いた声にソフィーはとんでもないわ!とすぐにハウルが魔法で用意したテーブルにセッティングしていく。マイケルも真っ青になってハウルに何事かを話していた。そういえば報告ってなんなのかしら?
花畑の奥を指差しながらあれこれと話しているマイケルの話をハウルは眉を寄せて聞いていた。水鏡の中でも食事の時間らしく薄汚れたテーブルの上で3人が向かい合っている。
「出来た、ソフィー?」
不意にかかった声に驚いて後ろを見るとハウルがじっと見つめてきていた。緑の瞳が一瞬だけ心配そうにソフィーを見ていた気がして首を傾げる。どうしたっていうのかしら?けれども訊こうと思ったときにはハウルはもうすでにいつもの笑顔でテーブルの上の料理に瞳を輝かせてソフィーは質問を諦めた。
「それじゃあ食べようか。」
「うわあ、美味しそうですね!」
駆け寄ってきたマイケルに当然だよと得意げに言ってハウルは席に着く。ソフィーは釈然としないまま二人にお茶を注ぐとハウルはにこやかに妻と弟子に笑いかけ、所狭しと並べられた料理に手を伸ばすのだった。
August 01, 2005